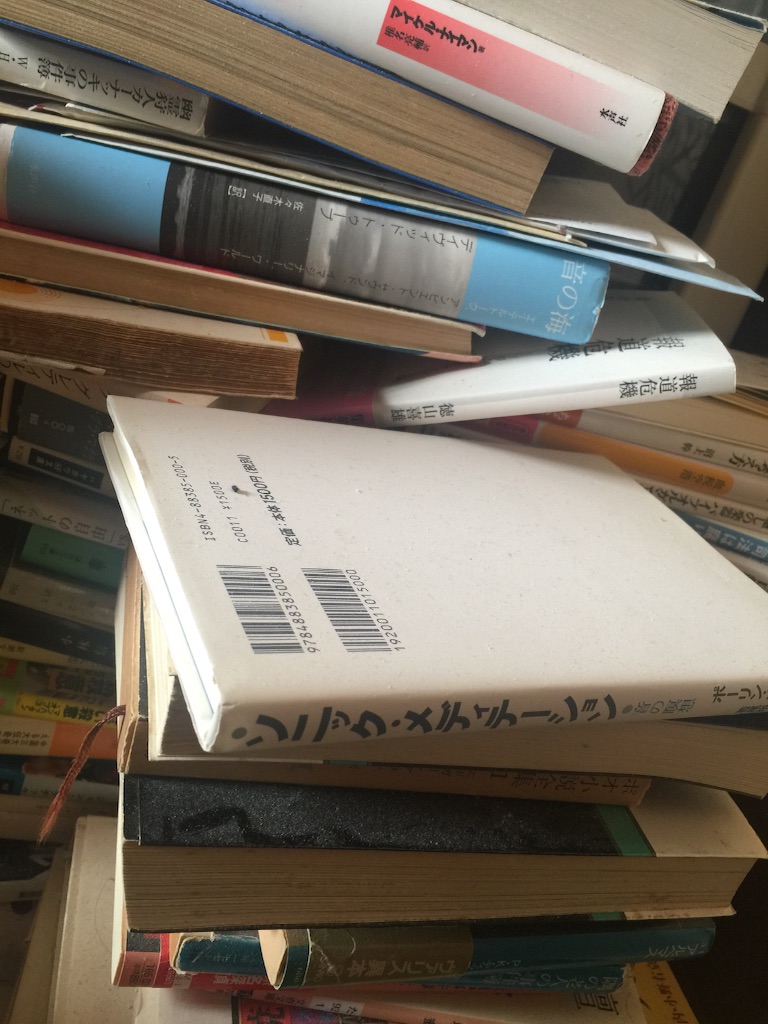本について考える出発点
少し前の記事だが、僕の古巣である落合書店の社長が読売新聞のインタビューに答えている。
この中に県書店商業組合のデータとして、2004年から13年までの県内書店数(組合加盟店のみ)が101から73に減ったと書かれている。約28%減だ。
こちらは全国のデータ。
2004年に18,156店舗だったのが、2014年には13,943店舗になっている。約24%減。
数字の規模が違い過ぎるので参考にしかならないけれども、まあ同じように減っていると考えていいだろう。
県書店商業組合にTSUTAYAなど大型書店がどの程度加盟しているかは不明だが、いずれにせよかなりの減少であり、小さい自治体では地元書店は壊滅している可能性もある。
インタビューでは新古書店の脅威についても触れられている。
ブックオフなどの新古書店は新刊書店にとっても従来の古書店にとっても脅威ということになっている。僕などは、新古書店にいっても欲しい本はなかなか無いのであまり見ないが、DVDやCDは熱心に探す。本についても熱心に探す人が多いのだろう。
以前に、古くからの宇都宮の古書店である山崎書店の店主が、
「うちはもう買い取りはやっていない。まるで儲からない、売れない」
「客はネットや新古書店に取られてしまった」
と嘆いていた。今では古書店もネット販売に積極的になっている。時代はどんどん流れている。
新古書店の一番の問題は、目利きができないこと。その本がどういう価値を持つのかは考慮されず、ただ新しい、古いだけで捌かれてしまう。
販売する方に目利きがいなければ、買う方も目利きできなくなる。本の価値を学ぶ場がなくなってしまうからだ。そこでは本は、徹底的に記号でしかない。
同様に通常のチェーン書店でも、本は基本的に記号でしかない。店員が努力しているところもあるが、通常は仕入れまで本部のコントロール下にあり、手書きポップでさえ共通化されているように見える。文言は違っても思考が同じなのだと感じてしまう。
どこにいっても同じ空間が提供されるチェーン店では、そこにある本も「書物」というより「記号」である。
非難しているのではない。
ある意味、僕にとっても本は情報であり記号である。
書物という、物理的なものに惚れ込んでいることは滅多にない。内容が全てである。
それは、チェーン店のスタンスと、実はほとんど変わらないのではないか。
そんなことを出発点にして、これから本について考えたいと思っている。